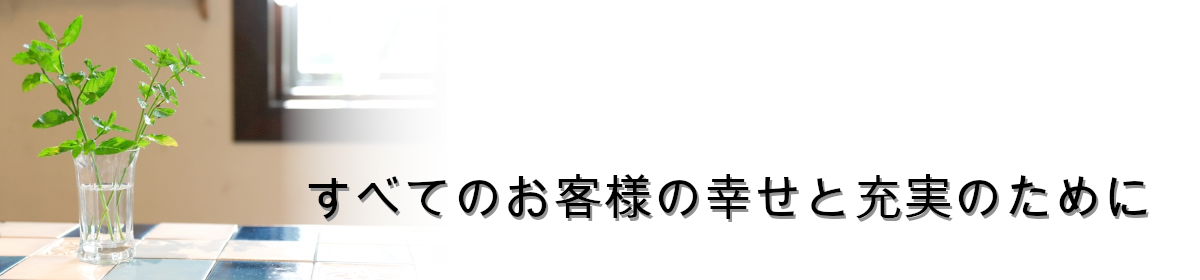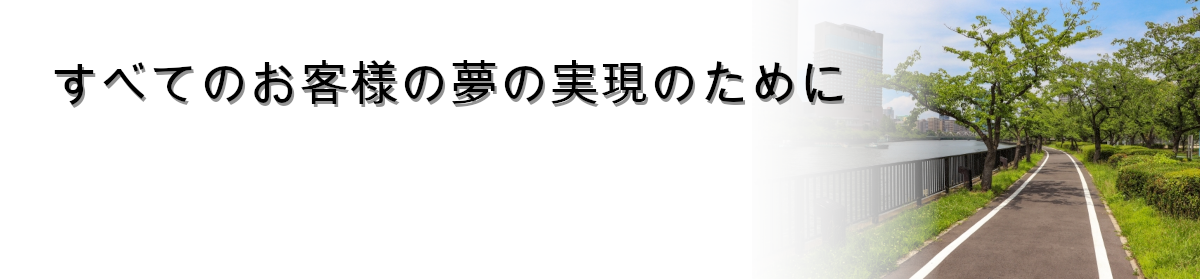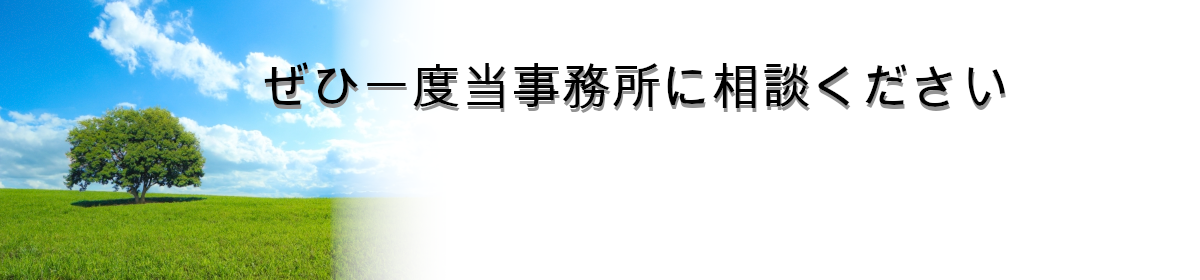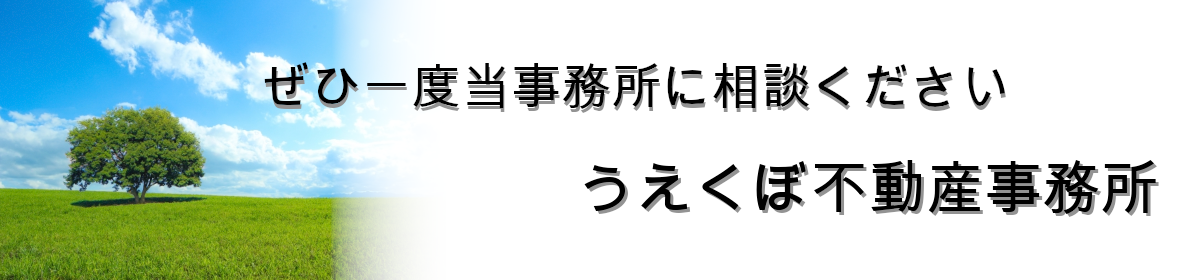1.Q:日本国籍がなくても不動産の売買契約できますか。
A:日本国籍がなくても契約は可能です。ただし、身分証明の方法や、契約内容の説明等に注意が必要です。また、外国為替及び外国貿易法等により報告書を提出する必要がある場合もあります。居住者と非居住者の区別が重要になることもあり、その他の規制にも注意が必要です。
2.Q:成年後見人が選任されている場合でも不動産の売却はできますか。
A:精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、一定の者の請求により家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人を「成年被後見人」といいます。成年被後見人の行為能力の制限は、行為制限制度の中で最も大きく、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて、全ての法律行為(売買契約の締結など)について常に取消すことができます。不動産売買契約も同様であり、成年被後見人が売買契約を締結したとしても、売買契約を取消すことができます。成年被後見人も、成年後見人が代理することで売買契約を締結することは可能です。しかしながら、売却する不動産が居住用の場合には、家庭裁判所の許可が必要であり、許可がなければいくら成年後見人が代理人として契約しても無効となります。
3.Q:保佐人が選任されている場合でも不動産売買契約の当事者になることはできますか。
A;精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者で、一定の者の請求により家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた人を「被保佐人」といいます。被保佐人が不動産の売買契約を締結するには裁判所が選任する保佐人の同意が必要です。保佐人の同意なく売買契約を締結したとしても、売買契約を取消すことができます。なお、保佐人は、法律上当然に代理権を持つ成年後見人と異なり、家庭裁判所が特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をしてはじめて、当該行為についての代理権を持つに至ります。したがって、保佐人との間で売買契約を締結する場合には、その売買契約の締結について保佐人に代理権があるのか等、事前に確認する必要があります。
4.Q:補助人が選任されている場合でも不動産売買契約の当事者になることはできますか。
A:精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者のうち、被後見人や被保佐人の程度に至らない軽度の状態にある者で、一定の者の請求により家庭裁判所から補助開始の審判を受けた人を「被補助人」といいます。被補助人は、補助人の同意を必要とするものとして審判で定められた法律行為(売買契約の締結など)については、補助人の同意を得る必要があり、補助人の同意なく売買契約を締結したとしても取消すことができます。したがって、不動産の売買契約について補助人の同意を得なければならないと定める審判がある場合には、補助人の同意が必要であり、補助人の同意なしに締結した売買契約は取消すことができます。なお、補助人についても、前述の保佐人と同様、補助人に一定の代理権を付与する審判が認められていますので、補助人を代理人として売買契約を締結できる場合があります。
5.Q:法人は不動産の売買契約の当事者になることはできますか。
A:法人が売買契約の当事者になることは可能です。その際、代表者が法人の意思を表示することになります。法人の代表者は、登記事項証明書または代表者事項証明書で確認することができます。
また、個人と同様、法人においても、実印は印鑑登録を証明する印として不動産の売買契約など重要な取引に使用されますので、法人の印鑑登録証明書をご用意頂く形になります。
6.Q:複数名が売買契約の当事者になることはできますか。
A:売主・買主の一方または双方が複数である場合があります。例えば、共有不動産の売却の場合は売主が複数となります。 注意点と対応策として、契約の当事者が2人以上の場合、契約に基づいて支払いを行う義務は均等に分割されるのが法律上の原則です。したがって、売買契約を締結した買主が2人の場合、売買契約に基づき売買代金を支払う義務は、2人に均等に分割されるため、2人の買主はそれぞれ売買代金を半分ずつ支払う義務しか負わないことになります。売主としては、どちらか一方の買主から支払ってもらえないときに、他方の買主に売買代金の全額を請求することはできないため、不利益を受ける可能性があります。また、契約に関する通知も、契約の当事者のうち1人だけではなく全員に通知しなければならないのが法律上の原則ですが、これは大変です。これらの注意点に対する対応策の一つとして、例えば、売買契約書の特約として「売主、買主の一方または双方が複数のとき、本契約に関する債務は連帯債務とします。」とか「本契約に関する通知は、複数の当事者のうちの1人に到達したときに、その全員に効力を生じます。」と定めておくことが考えられます。
前者のように「連帯債務」と定めた場合には、契約に基づいて支払いを行う義務は分割されず、それぞれの当事者が全額を支払う義務を負うことになります。また、後者のように、1人に対する通知で当事者全員に通知の効力が生じると定めた場合には、当事者全員に対して通知を行う必要はないことになります。
7.Q:代理人と不動産の売買契約を締結することはできますか。
A:代理人による売買契約の締結は可能です。代理人には大きく分けて法定代理人、任意代理人の2つがあります。法定代理人は、代理権の発生が法律の規定(裁判所による選任も含みます。)によるものです。任意代理人は、本人から代理権を与えられたことにより代理権が発生するものです。
8.Q;他人の土地や家の不動産所有情報はどのように確認できますか。
A:不動産は重要な財産ですから、取引をするに当たって、誰が所有しているのか、また、広さはどの程度か、などの情報が大変重要になります。そこで、不動産についての情報を国家機関が登録し、一般に公表することとしています。このような制度を「登記」といいます。不動産について登記されている情報は、法務局(または地方法務局、支局、出張所)で申請することにより、誰でも自由に入手することができます。また、法務局では不動産について登記されている情報を証明する書面を入手することができますが、このような書面には「全部事項証明書」と「現在事項証明書」があります。全部事項証明書には、抹消された登記を含む全ての内容が記載され、現在事項証明書には、現在時点で効力のある内容だけが記載されます。調査の目的によって選択する必要がありますが、より多くの情報を得たい場合には、全部事項証明書の方が適切といえます。
9.Q:土地の全部事項証明書の表題部にはどのようなことが記載されているのでしょうか。
A:土地の全部事項証明書は、上から順に「表題部(土地の表示)」、「権利部(甲区)(所有権に関する事項)」、「権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)」に分かれています。
「表題部(土地の表示)」には、土地を特定するための情報が記載されており、所在、地番、地目、地積などの欄に分かれています。
所在については、土地の位置を特定するためのもので、市区町村、及び、丁目・字(あざ)までが記載されます。
地番とは、登記上で土地を特定するために1筆ごとの土地につけられた番号をいいます。
地目とは、土地の用途をいいます。宅地、田、畑、山林、原野、雑種地、公衆用道路など、法律で定められた種類のうちの一つが選択されています。
地積とは、土地の面積をいいます。
なお、登記されている地積が、実際の土地の正確な面積とは異なっていることがよくあります。測量技術が発達していない時代に登記された土地もあることなど、いろいろな原因があると言われています。また、全部事項証明書に記載されている地積を「公簿面積」と言い、一般的な不動産の売買ではこの「公簿面積」を見ます。
10.Q:建物の全部事項証明書の表題部にはどのようなことが記載されているのでしょうか。
A:建物の全部事項証明書は、上から順に「表題部(主である建物の表示)」、「権利部(甲区)(所有権に関する事項)」、「権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項)」に分かれています。
建物の全部事項証明書の表題部は、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、原因及びその日付などの欄に分かれています。
所在とは、建物の位置を特定するためのものですが、土地の所在とは異なり、地番まで記載されます。
家屋番号とは、建物を特定するための番号をいいます。通常、建物が建っている敷地の地番と同じ番号を使うことになっていますが、同じ敷地に複数の建物が建っている場合には、「○番の1」と「○番の2」のように枝番をつけて区別されます。
種類とは、建物の用途をいいます。法律の定めはなく、居宅、店舗、倉庫など、用途に応じた記載がされます。
構造とは、建物の主要構造部の状況(木造か鉄骨造か等)、屋根の状況(瓦葺か陸屋根か等)、階数を記載するものです。
床面積の欄には、建物の広さが各階ごとに記載されます。
「原因及びその日付」の欄には、登記をする原因となった事柄、及び、その事柄が生じた年月日が記載され、例えば建物の新築の年月日はこの欄に記載されます。
一覧に戻る