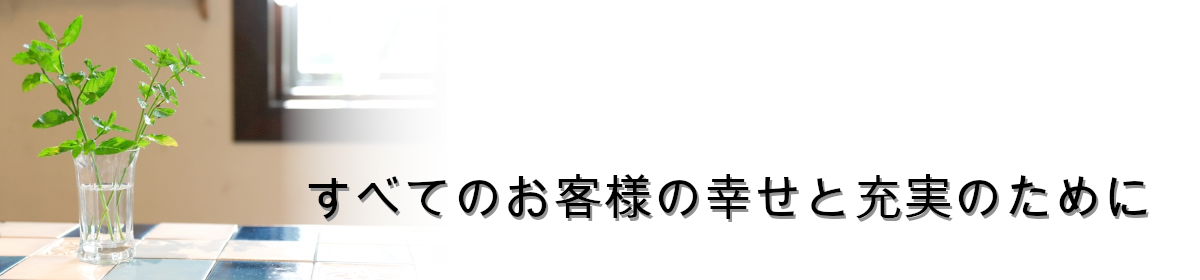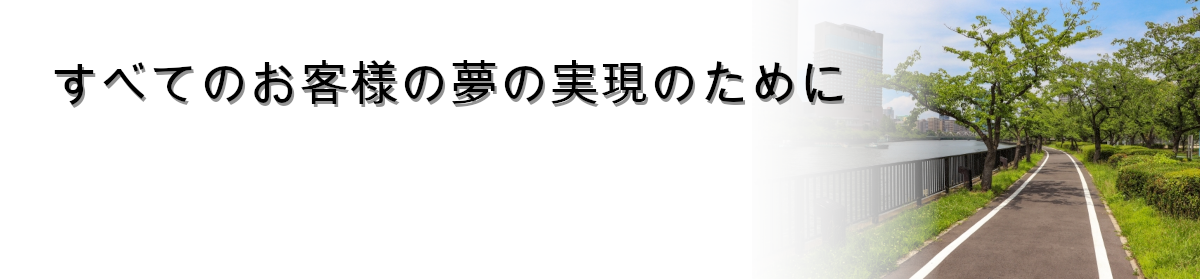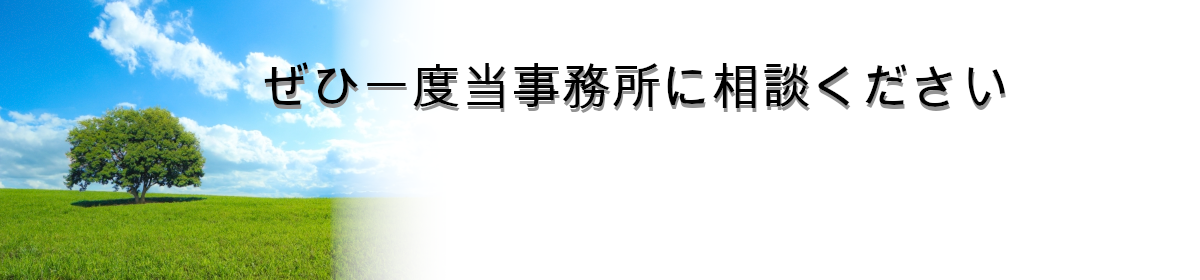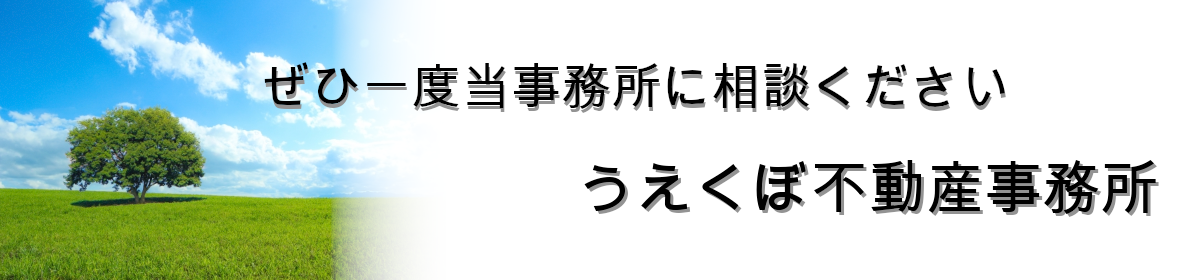1.Q:収入印紙代は、売主と買主のどちらが負担するのですか。
A:売買契約などについて定めた民法では、「売買契約に関する費用」は、売主と買主の双方が平等に負担することとされています。印紙代も「売買契約に関する費用」ですので、売主と買主が平等に負担しなければなりません。印紙税法では、印紙税の納税義務は、文書の作成名義人の連帯責任とされています。そのため、売主と買主は、それぞれ連帯して印紙税を納める責任を負っていることになります。このような民法、印紙税法上の決まりを踏まえて、不動産の売買契約書には、「印紙代は、各自が平等に負担する。」などと規定して、売主、買主各自が保有する契約書に各自が印紙を貼付するというようにされているのが一般的です。もっとも、売主と買主の間の特約で、例えば、「売主が印紙代を全額負担する。」といった合意をすれば、そのような合意は売主と買主の間では有効になります。
2.Q:不動産売買契約書にある「管轄裁判所」とはどこですか。
A:管轄裁判所とは、不動産の売買契約に関する訴訟を提起する場合にその訴訟を行うことができる裁判所のことをいいます。例えば、個人である買主が購入した土地について、個人である売主に対して土地の移転登記手続を請求する訴訟を起こす場合には、売主の住所地と購入した土地の所在地の裁判所に管轄があることになります。管轄裁判所は、民事訴訟法などの法律で定められています。
3.Q:不動産売買契約書で管轄裁判所を定めることには何か意味がありますか。
A;訴訟を行うことができる裁判所は法律上決まっているのですが、どこの裁判所で訴訟をするかということを事前に当事者の合意で定めておくことができます。不動産の売買契約書にも、このような事項を定めた管轄裁判所の合意が規定されていることが多いです。管轄裁判所を定めておくことによって、法律上決まっている裁判所以外の場所の裁判所でも訴訟を起こすことができます。また、訴訟を起こすのであれば契約書で定めた場所の裁判所に限定するといった合意をすることもできます。一定の例外はあるものの、民事裁判では、原則として当事者または代理人が裁判所に直接出頭しなければなりません。また、事案によっては、裁判が長期化することもあります。そのため、事前に管轄裁判所を定めておくことにより、万一、訴訟が起こってしまった場合に、遠方の裁判所まで出頭しなければならないというリスクを回避することができます。
4.Q:ある条件を満たした場合にだけ効力が生じるような不動産売買契約はできますか。また、ある条件を満たした場合には効力が失われるような契約はできますか。
A:いずれもできます。
ある条件を満たした場合にだけ効力が生じるような条件を「停止条件」といいます。
例えば、大学を卒業したら、あの家を50万円で売ってあげるという合意は、「大学を卒業すること」が停止条件となっているといえます。
また、ある条件を満たした場合には契約の効力が失われるような条件を「解除条件」といいます。
例えば、建物を購入するために必要となる銀行の融資を受けられなかったときは、売買契約の効力が消滅するという合意は、「銀行の融資を受けられなかったこと」が解除条件になっているといえます。
以上のように、売買契約において条件(停止条件または解除条件)を定めることができますが、不法な条件を付けた合意は無効になります。
例えば、覚せい剤をくれたらこの土地を100万円で売るなどという合意は、無効になります。
5.Q:不動産売買契約書の内容が不明確な場合や納得できない場合はどうすれば良いですか。
A:不動産売買契約書に署名・捺印した場合には、原則としてその契約書に書いてある内容について売主と買主が合意したものと判断されます。そのため、売買契約書の内容が不明確でよく分からない箇所があったり、その内容に納得できなかったりする場合には売買契約書に署名・捺印する前に内容をしっかりと確認する必要があります。また、契約の内容を明確にしてもらったり、納得できる内容にしてもらったりできないか、契約の修正を求めたり、特約を設けたりするように交渉すべきでしょう。
6.Q:マンション投資を考えているのですが、自己資金が少なくローンを活用し購入しようと考えております。 自己資金をあまり入れずにローンを組んで物件を購入することは危険でしょうか。
A:危険だと私は思います。ただし、繰上返済することで、早期完済できるなら大丈夫でしょう。
空室や滞納、家賃下落など、数あるマンション投資のなかでも、最大のリスクが『借金(ローン)』です。
ローンを借りている間、金利がずっと固定され、空室や家賃下落、滞納などの問題がなければ、ローンを利用して物件を購入しても問題はないでしょう。しかし、実際には、金利の変動はありますし、空室がまったくないことも考えられません。
空室や滞納が長期間続けば、毎月のローン返済額の全額を自分で支払わなければならなくなります。空室や滞納があったとしても、ローンを完済していれば、オーナーの自己負担は毎月1万~1万5千円程度の管理費修繕積立金で済みます。
バブル崩壊時にマンション投資で失敗したひとは空室や滞納で破綻したわけではありません。多くの方が多額の借金を抱えていて、借り入れ負担に耐え切れなくなったのです。
特に、ご注意頂きたい手法が頭金ゼロで地方の1棟アパートに投資をする行為です。サブリース契約(空室保証)があるからといっても、将来賃料は引き下げられることもあり、賃料の引き下げに応じなければ解約されてしまうこともあります。それに加えて金利の上昇や滞納が発生すると、多額の借り入れ負担には一般のサラリーマンは対応しきれないはずです。
より安全にマンション投資を行なっていくのであれば、借り入れ金を繰上返済して、上手にコントロールしていくことが欠かせません。
7.Q:自宅のローンがまだ残っているのですが、投資用のローンを組むことはできるのでしょうか?
A:ご自宅のローンが残っていても、投資用のローンを利用することは可能です。
ただし、お借入の残額やご年収、勤務先などの諸条件によって融資の可否や金額、借入年数が判断されます。
当社では事前にある程度の内容を確認させていただければ、速やかにご返答が可能ですので、お気軽にご相談ください。
8.Q;投資用のローンと、自宅を購入するための住宅ローンとの違いを教えて下さい。
A:自宅用のローンと投資用物件購入のためのローンは審査基準、金利条件の面で異なります。
自宅用ローンは債務者の返済意思が高いことから、投資用ローンに比べて、審査基準も緩和されています。
また、自宅用ローンの金利水準も自宅用ローンの需要も比較的多いことから、返済意思の両面から低金利になっています。
9.Q:ローンを組んで物件を購入した後、自分が死亡した場合、購入した物件やローンはどうなるのでしょうか?
A:投資用ローンでも、自宅用ローンと同じように『団体信用生命保険』が付きます。
ご自身に万が一のことがあった際には、ローンは完済され、借り入れのない収益不動産を家族に遺すことができます。マンション投資は資産運用の手段だけではなく、将来の家族の生活を守ることの出来る優れた商品です。また、団体信用生命保険は文字通り『団体』加入となるので、一般の生命保険とは異なり、加入年齢によっても支払う保険料の金額は変わりません。たとえば、一般的な生命保険の場合、30歳の人と50歳の人では、毎月の保険料は3倍くらい違ってきますが、団体信用生命保険ならば、30歳でも50歳でも保険料の金額は変わらないのです。
ローンを利用できる現役世代にとって、団信を使ったマンション投資は少ない自己資金で家族に財産を残せる投資法です。
10.Q:既に住宅ローンで団体信用生命保険に加入していますが、投資用マンション購入で新たに団信に加入できますか?
A:団体信用生命保険は自宅用のローンですでに加入していても、投資用ローンの団体信用生命保険に加入することが可能です。自宅と投資用物件だけでなく、複数の投資用不動産を所有していた場合にも、物件ごとに加入できます。